こんにちは。今回は2020年東工大数学大問5の解説をします。
問題
\(k\) を正の整数とし、
$$a_k=\int_{0}^{1}x^{k-1}\sin{\frac{\pi x}{2}}dx$$
とおく。
(1) \(a_{k+2}\) を \(a_k\) と \(k\) を用いて表せ。
(2) \(k\) を限りなく大きくするとき、数列 {\({ka_k}\)} の極限値 \(A\) を求めよ。
(3) (2)の極限値 \(A\) に対し、\(k\) を限りなく大きくするとき、数列 {\(k^ma_k-k^nA\)} が\(0\) ではない値に収束する整数 \(m\),\(n\) (\(m>n\ge 1\)) を求めよ。また、そのときの極限値 \(B\) を求めよ。
(4) (2)と(3)の極限値 \(A\) \(B\) に対し、\(k\) を限りなく大きくするとき、数列 {\(k^pa_k-k^qA-k^rB\)} が \(0\) でない値に収束する整数 \(p\),\(q\), \(r\) (\(p>q>r\ge 1\)) を求めよ。また、そのときの極限値 \(C\) を求めよ。
答案例
(1)
$$a_k=\int_{0}^{1}x^{k-1}\sin{\frac{\pi x}{2}}dx \tag{1}$$
式(1)より、
$$a_{k+2}=\int_{0}^{1}x^{k+1}\sin{\frac{\pi x}{2}}dx$$
$$=\left[x^{k+1}\frac{-2}{\pi}\cos{\frac{\pi x}{2}}\right]_0^1 +\int_{0}^{1}(k+1)x^k \frac{2}{\pi}\cos{\frac{\pi x}{2}}dx$$
$$=\left[(k+1)x^k \left(\frac{2}{\pi}\right)^2 \sin{\frac{\pi x}{2}}\right]_0^1-\int_{0}^{1} (k+1)kx^{k-1} \left(\frac{2}{\pi}\right)^2 \sin{\frac{\pi x}{2}}dx$$
$$=(k+1)\frac{4}{\pi^2}-(k+1)k\frac{4}{\pi^2}a_k$$
$$∴\space a_{k+2}=(k+1)\frac{4}{\pi^2}\left(1-ka_k\right) \tag{2}$$
である。
(2)
\(A_k=ka_k\) とし、極限値 \(A=\lim_{k \to \infty} A_k\) を求める。式(2)より、
$$ka_k=A_k=1-\frac{\pi^2}{4}\frac{a_{k+2}}{k+1} \tag{3}$$
である。ここで、 \(a_{k+2}\) の定積分について、 \(0<x<1\) で常に
$$0<x^{k+1} \sin{\frac{\pi x}{2}}<x^{k+1}$$
が成立することから、辺々を \(0<x<1\) で積分すると、
$$\int_{0}^{1} 0 dx<\int_{0}^{1} x^{k+1} \sin{\frac{\pi x}{2}} dx<\int_{0}^{1} x^{k+1}dx$$
$$\Rightarrow 0<a_{k+2}<\frac{1}{k+2} \tag{4}$$
が得られ、式(4)右端は \(k \to \infty \) で \(\frac{1}{k+2} \to 0\) に収束するため、はさみうちの原理より、
$$\lim_{k \to \infty } a_{k+2}=0 \tag{5}$$
が得られる。式(3)(5)より、
$$A=\lim_{k \to \infty}\left(1- \frac{\pi^2}{4}\frac{a_{k+2}}{k+1}\right) =1$$
である。
(3)
\(B_k=k^m a_k -k^n A \space (m>n\ge 1)\) とおき、 \(\lim_{k \to \infty}B_k\) が \(0\) でない極限値 \(B\) に収束するための必要条件を考える。
問(1)の結果から、
$$B_k=k^m a_k-k^nA=k^{m-1}ka_k-k^n \cdot 1=k^{m-1}A_k-k^n$$
$$\Rightarrow B_k=k^n (k^{m-n-1}A_k-1)$$
と変形でき、 \(k \to \infty\) の極限では \(k^n \to \infty,\space A_k \to 1\) となることから、 \(B_k\) が非0の極限値を持つためには、
$$k^{m-n-1}A_k-1 \to 0 \space (k \to \infty)$$
$$\Rightarrow k^{m-n-1} \to 1 \space (k \to \infty)$$
$$\Rightarrow m-n-1=0 \tag{6}$$
が必要である。このとき、
$$B_k=k^n(A_k-1)=k^n \left(-\frac{\pi^2}{4}\frac{a_{k+2}}{k+1}\right) \space (∴式(3))$$
$$\Rightarrow B_k=-\frac{\pi^2}{4}\frac{k^2 A_{k+2}}{(k+2)(k+1)} k^{n-2} \tag{7}$$
と表される。 \(k \to \infty\) の極限で \(\frac{k^2}{(k+2)(k+1)} \to 1\)であり、問(2)で \(A_k \to 1\) を求めたのと同様の手順で \(\space A_{k+2} \to 1\) が導けるため、式(7)より \(B_k\) が非0の極限値を持つためには、
$$k^{n-2} \to 1 \space (k \to \infty)$$
$$\Rightarrow n-2=0 \tag{8}$$
が必要で、このとき
$$\lim_{k \to \infty}B_k=\lim_{k \to \infty}\left(-\frac{\pi^2}{4}\frac{k^2 A_{k+2}}{(k+2)(k+1)})\right)= -\frac{\pi^2}{4} \tag{9}$$
となる。式(6)(8)(9)より、 \(k^m a_k -k^n A\) は \((m,n)=(3,2)\) の場合のみ0でない極限値 \(B=-\frac{\pi^2}{4}\) をもつ。
(4)
\(C_k=k^p a_k-k^q A-k^r B \space (p>q>r \ge 1)\) とおき、 \(\lim_{k \to \infty}C_k\) が \(0\) でない極限値 \(C\) に収束するための必要条件を考える。
問(1)(2)の結果から、
$$C_k=k^{p-1} A_k-k^q-Bk^r=k^q\left(k^{p-q-1}A_k-1-Bk^{r-q}\right)$$
と変形でき、 \(k \to \infty \) の極限において \(k^q \to \infty,\space k^{r-q} \to 0,\space A_k \to 1\) となることから、 \(C_k\) が非0の極限値をもつためには、
$$k^{p-q-1}A_k-1 \to 0 \space (k \to \infty)$$
$$\Rightarrow p-q-1=0 \tag{10}$$
が必要である。このとき、 \(B_k=k^2(A_k-1)\) より、
$$C_k=k^q\left(A_k-1-Bk^{r-q}\right)$$
$$=k^q (A_k -1)-Bk^r$$
$$=k^{q-2} k^2(A_k-1)-Bk^r$$
$$=k^{q-2}B_k-Bk^r$$
$$=k^r(k^{q-r-2}B_k-B)$$
と変形でき、 \(k \to \infty \) の極限において \(k^r \to \infty,\space B_k \to B\) となることから、 \(C_k\) が非0の極限値をもつためには、
$$B_k k^{q-r-2} -B \to 0 \space (k \to \infty)$$
$$\Rightarrow q-r-2=0 \tag{11}$$
が必要である。このとき、
$$C_k=k^r(B_k-B)$$
と表現できる。
ここで、式(3)に \(B_k=k^2(A_k-1),\space B_{k+2}=(k+2)^2(A_{k+2}-1)\) を用いると、
$$式(3)\Leftrightarrow A_k-1=B\frac{A_{k+2}}{(k+2)(k+1)}$$
$$\Leftrightarrow \frac{B_k}{k^2}=B\frac{1}{(k+2)(k+1)}\left(\frac{B_{k+2}}{(k+2)^2}+1\right)$$
$$\Leftrightarrow B_k-B=B\frac{k^2}{(k+2)(k+1)}\left(\frac{B_{k+2}}{(k+2)^2}+1\right)-B$$
$$=B\left(\frac{k^2}{(k+2)^3(k+1)}B_{k+2}+\frac{k^2}{(k+2)(k+1)}-1\right)$$
$$=B\left(\frac{k^2}{(k+2)^3(k+1)}B_{k+2}+\frac{k^2-(k+2)(k+1)}{(k+2)(k+1)}\right)$$
$$=B\left(\frac{k^2}{(k+2)^3(k+1)}B_{k+2}-\frac{3k+2}{(k+2)(k+1)}\right)$$
$$\Leftrightarrow C_k=k^r(B_k-B)=Bk^{r-1}\left(\frac{k^3}{(k+2)^3(k+1)}B_{k+2}-\frac{k(3k+2)}{(k+2)(k+1)}\right)$$
と変形でき、問(3)で \(B_k \to B \space (k \to \infty)\) を求めたのと同様の手順で \(B_{k+2} \to B \space (k \to \infty)\) が求まることに留意すれば、 \(k \to \infty \) の極限において \(\frac{k^3}{(k+2)^3(k+1)}B_{k+2} \to 0, \space \frac{k(3k+2)}{(k+2)(k+1)} \to 3\) となるため
$$\frac{k^3}{(k+2)^3(k+1)}B_{k+2}-\frac{k(3k+2)}{(k+2)(k+1)} \to -3 \space(k \to \infty)$$
に収束する。よって、 \(C_k\) が非0の極限値を持つためには
$$k^{r-1} \to 1 \space (k \to \infty)$$
$$\Rightarrow r-1=0 \tag{12}$$
が必要となり、このとき
$$\lim_{k \to \infty}C_k=\lim_{k \to \infty}B\left(\frac{k^3}{(k+2)^3(k+1)}B_{k+2}-\frac{k(3k+2)}{(k+2)(k+1)}\right)=-3B=\frac{3\pi^2}{4} \tag{13}$$
となる。式(10)(11)(12)(13)より、 \(k^p a_k-k^q A-k^r B\) は \((p,q,r)=(4,3,1)\) の場合のみ0でない極限値 \(C=\frac{3\pi^2}{4}\) をもつ。
解説
数列の収束・発散について考察する極限の問題です。極限分野の基礎中の基礎である「不定形」の処理についてゴリゴリに深掘る問題です。
(4)まで完答する難易度は東工大基準でも「難」ですが、(1)(2)は標準、(3)は標準~やや難くらいなので、最低でも(2)までは粘りたいところです。(3)まで解ければ十分に合格圏内でしょう。(4)は極限ガチ勢向けです。
全体を通して重要なポイントは下記4点です。
- 数列 \(\alpha_k\) が発散、数列 \(\alpha_k \beta_k\) が収束する \(\Rightarrow\) 数列 \(\beta_k\) は \(0\) に収束する。(必要条件)
- 不定形処理では「 \(0\) でない値に収束するカタマリ」を目指して式変形する。
- \(\infty-\infty\) のタイプの不定形は強い方(or 弱い方)で括る。
- \(\infty \times 0\) のタイプの不定形は “\(0\)” の側を掘り下げる。
(1)
定積分で書かれた \(a_k\) の一般項をもとに、 \(a_{k+2}\) と \(a_k\) の関係式を作る問題です。
部分積分を利用して \(a_{k+2}\) の定積分から \(a_k\) を取り出します。 \(a_{k+2}\) の被積分関数 \(x^{k+1}\sin{\frac{\pi x}{2}}\) について、 \(x^{k+1}\) の次数を下げたいので、相方の \(\sin{\frac{\pi x}{2}}\) を積分する側に選びます。符号ミスに注意して丁寧に計算しましょう。
(2)
「数列 \(ka_k\) の極限値 \(A\) を求めよ。」という問題です。「極限」ではなく「極限値」であることが重要です。「極限を求めよ」という問題文の場合、求める極限の発散 or 振動 or 収束が判断できませんが、「極限値」なので \(ka_k\) が有限の値に収束することを問題文が教えてくれている訳です。東工大レベルにもなると、この種のさりげないヒントに目敏く反応できるか否かが合否に直結します。
数列 \(ka_k\) について、これは \(k\) と \(a_k\) の掛け算の形をとっており、 \(k\) は \(k \to \infty\) の極限において \(\infty\) に発散します。このとき、 \(ka_k\) が極限値 \(A\) を持つためには、相方の \(a_k\) が \(0\) に収束しなければいけません。このことから、求める極限 \(ka_k\) は \(\infty \times 0\) のタイプの不定形であることが読み取れます。
上記を念頭に、(1)で得られた漸化式を \(ka_k\) について解いてみます。
$$a_{k+2}=(k+1)\frac{4}{\pi^2}(1-ka_k)$$
$$\Leftrightarrow ka_k=1-\frac{\pi^2}{4}\frac{a_{k+2}}{k+1}$$
上式左辺を \(A_k=ka_k\) とし、これの極限を求めます。右辺について、 \(a_k\) が \(0\) に収束することは掴めているので、 \(a_{k+2}\) も \(0\) に収束することが期待できます。仮にそうだとすれば、 \(\frac{a_{k+2}}{k+1}\) は \(0\) に収束するので上式右辺の極限は \(1-0=1\) ということになり、目的の極限値が \(A=1\) と求まります。
従って、(2)は \(a_{k+2} \to 0\) を示すことが実質的なゴールになります。これは、与えられた定積分を評価することで示すことができます。
$$a_{k+2}=\int_{0}^{1}x^{k+1}\sin{\frac{\pi x}{2}}dx$$
被積分関数 \(x^{k+1}\sin{\frac{\pi x}{2}}\) について、 \(\sin{\frac{\pi x}{2}}\) は \(0<x<1\) で単調増加なので値域は \(0<\sin{\frac{\pi x}{2}}<1\) となります。 \(x^{k+1}\) は同区間で正値をとるので、 \(0<x<1\) では下記の不等式が成立します。
$$0<x^{k+1}\sin{\frac{\pi x}{2}}<x^{k+1} \space (0<x<1)$$
上の不等式の辺々を \(0<x<1\) で積分すれば、
$$\int_{0}^{1} 0 dx<\int_{0}^{1} x^{k+1} \sin{\frac{\pi x}{2}} dx<\int_{0}^{1} x^{k+1}dx$$
$$\Rightarrow 0<a_{k+2}<\frac{1}{k+2}$$
という不等式が得られ、右端 \(\frac{1}{k+2}\) が \(0\) に収束することから、はさみうちの原理より \(a_{k+2}\) の極限値は \(0\) ということになります。
以上より、 \(A_k=1-\frac{\pi^2}{4(k+1)}a_{k+2}\) の極限値は \(A=1\) となります。
(3)
数列 \(k^m a_k-k^n A\) が \(0\) でない極限値 \(B\) をもつ為の自然数 \(m>n\) の条件と極限値 \(B\) を求める問題です。(3)も極限「値」という情報が取っ掛かりになります。
まずは題意の数列を \(B_k=k^m a_k-k^n A\) とおき、\(B_k\) の不定形を処理していきましょう。(1)より \(A=1\) なので \(B_k=k^m a_k-k^n \) と書け、 \(k \to \infty \) で \(a_k \to 0\) に収束することから、 \(B_k\) は \(\infty \times 0 – \infty\) のタイプの不定形と解釈できます。
\(B_k\) の不定形を処理していきます。ポイントは \(0\) でない値に収束するカタマリを意識することです。 \(B_k=k^m a_k-k^n\) について、(1)より \(A_k=ka_k\) は \(1\) に収束するため不定形が解消できていることを利用すれば、 \(B_k=k^{m-1}ka_k-k^n=k^{m-1}A_k-k^n\) と書き換えられ、 \(\infty-\infty\) のタイプの不定形として考察ができます。
\(\infty-\infty\) の不定形は強い方(or 弱い方)で括るのが定石です。強い方と弱い方どちらで括るかは問題によります。大した手間でもないので両方試してみるのがいいと思います。今回は弱い方 \(k^n\) で括るのが吉です。
$$B_k=k^{m-1} A_k-k^n$$
$$=k^n(k^{m-n-1} A_k-1)$$
\(B_k=k^n(k^{m-n-1} A_k-1)\) の極限について考察します。 \(k^n\) は \(\infty \) に発散するので、 \(B_k\) が \(0\) でない収束値を持つためには \(\infty \times 0\) の不定形となっている必要があります。従って、 \(B_k\) が \(B \neq 0\) に収束するためには \(k^{m-n-1}A_k-1\) が \(0\) に収束することが必要となります。 \(k^{m-n-1}A_k-1\) は次数の \(m-n-1\) が0より大きい場合は \(+\infty\) に発散、0より小さい場合は \(0-1=-1\) に収束、 \(m-n-1=0\)の場合は \(1-1=0\) に収束します。従って、 \(m-n-1=0\) が確定します。
このように、 \(\infty \times 0\) の不定形が \(\neq 0\) に収束するための必要条件という着眼点が大問全体を通して重要になってきます。
以上より \(B_k=k^n(A_k-1)\) と書け、 \(\infty \times 0\) の不定形の形が見えてきます。 \(\infty \times 0\) の不定形は \(0\) の側を掘り下げるのがコツです。よって今回は \(A_k-1\) について掘り下げてみます。
\(A_k-1\) を考察すべく、(1)で作った \(a_{k}\) の漸化式をみてみます。ここでも \(0\) でない値に収束するカタマリが欲しいので、 \(A_k=ka_k, \space A_{k+2}=(k+2)a_{k+2}\) を用いて書き換えてみましょう。
$$a_{k+2}=(k+1)\frac{4}{\pi^2}(1-ka_k)$$
$$\Leftrightarrow ka_k-1=-\frac{\pi^2}{4}\frac{a_{k+2}}{k+1}$$
$$\Leftrightarrow A_k-1=-\frac{\pi^2}{4}\frac{1}{(k+2)(k+1)}A_{k+2}$$
上式の両辺に \(k^n\) を掛ければ \(B_k\) を \(A_{k+2}\) で表現できます。
$$B_k=k^n (A_k-1)=-\frac{\pi^2}{4}\frac{1}{(k+2)(k+1)}A_{k+2}k^n$$
上式右端の不定形について考えてみます。ここでも \(0\) でない値に収束するカタマリを意識しましょう。右辺の \(\frac{1}{(k+2)(k+1)}\) の項は \(0\) に収束する訳ですが、分母が2次式であることを踏まえれば、 \(k^2\) を掛けて \(\frac{k^2}{(k+2)(k+1)}\) とすれば \(1\) に収束するカタマリになります。これを踏まえて式変形すれば不定形を含まない表式を得ることができます。
$$B_k=-\frac{\pi^2}{4}\frac{k^2}{(k+2)(k+1)}A_{k+2}k^{n-2}$$
式変形が完了したので、改めて \(B_k\) が \(0\) でない極限値 \(B\) をもつ条件を考えます。上式右辺の \(k^{n-2}\) 以外の項はすべて \(0\) でない収束値をもつため、 \(B_k\) は \(n-2>0\) のとき発散、 \(n-2<0\) のとき \(0\) に収束します。従って、 \(B_k\) が \(0\) でない値に収束するためには、ぴったり \(n-2=0\) である必要があり、このとき
$$B_k=-\frac{\pi^2}{4}\frac{k^2}{(k+2)(k+1)}A_{k+2}$$
は \(-\frac{\pi^2}{4}\) に収束するため、これが求める値 \(B\) ということになります。以上より、 \(m=3,n=2,B=-\frac{\pi^2}{4}\) が最終的な解答になります。
(4)
数列 \(k^p a_k-k^q A-k^r B\) が \(0\) でない極限値 \(C\) をもつ為の自然数 \(p>q>r\) の条件と極限値 \(C\) を求める問題です。やることは(3)とほぼ同じです。まずは題意の数列を \(C_k=k^{p-1} A_k-k^q +\frac{\pi^2}{4} k^r\) とおき、(3)と同様の手順で \(C_k\) の不定形を考察してみます。
\(k^{p-1}A_k,\space k^q,\space k^r\) はすべて \(\infty\) に発散するため、 \(C_k\) は \(\infty-\infty+\infty\) の不定形となっています。今回のような \(\infty\) が3つ以上足し引きされている不定形では、発散のスピード(オーダー)に着目しましょう。式中の3項目の \(\frac{\pi^2}{4}k^r\) のオーダーは \(k^r \) ですが、1項目の \(k^{p-1}A_k\) のオーダー \(k^{p-1}\) より明らかに弱いため、3項目は無視して考えることができます。従って、 \(C_k\) は正に発散する \(k^{p-1}A_k\) と負に発散する \(-k^q\) の2項に絞って考察すれば十分です。
今回も(3)と同様に弱い方 \(k^q\) で括ってみましょう。 \(-\frac{\pi^2}{4}\) はただの定数なので \(B\) に戻しておきます。
$$C_k=k^q(k^{p-q-1}A_k-1-Bk^{r-q})$$
\(k^{r-q}\) が \(0\) に収束することに留意しながら(3)と全く同様の手順で \(C_k\) が非0の収束値をもつ条件を考察すると、 \(p-q-1=0\) が得られ、 \(C_k\) は、
$$C_k=k^q(A_k-1-Bk^{r-q})$$
$$=k^q( A_k-1)-Bk^r$$
と変形できます。上式の不定形は \(\infty \times 0 – \infty\) のような形になっているので、この不定形の解消を目指します。ここでも、0でない値に収束するカタマリを狙います。 \(k^q(A_k-1)\) は \(\infty \times 0\) の不定形ですが、(3)で得られた知見より、 \(B_k=k^2(A_k-1)\) は \(B \neq 0\) に収束するため、 \(k^q(A_k-1)=k^{q-2}k^2(A_k-1)=k^{q-2}B_k\) と変形すれば不定形を解消することができます。これを用いると \(C_k\) は
$$C_k=k^{q-2} \times k^2(A_k-1)-Bk^r$$
$$∴ \space C_k=k^{q-2}B_k-Bk^r$$
と変形でき、ここでも弱そうな方 \(k^r\) で括ってあげれば、
$$C_k=k^r(k^{q-r-2}B_k-B)$$
となり、不定形の考察ができる形になります。 \(k^r\) は \(\infty\) に発散し、 \(B_k\) は \(B\) に収束するので、 \(C_k\) が \(C \neq 0\) に収束するための必要条件を考えれば、 \(q-r-2=0\) が得られ、
$$C_k=k^r(B_k-B)$$
が得られます。
試験時間中にこの辺りまで辿り着ければ十分に合格ラインだと思います。
この先は極限ガチ勢向けです。
\(C_k=k^r(B_k-B)\) の不定形を切り崩したい訳ですが、この表式をよく観察すると、問(3)で出てきた \(B_k=k^n(A_k-1)\) と酷似していることがわかるかと思います。 \(B_k\) の \(\infty \times 0\) の不定形を解消する際、 \(A_k-1\) を \(A_{k+2}\) で書き換えることが突破口になったことを思い出せば、(4)も \(B_k-B\) を \(B_{k+2}\) で書き換えればいいのでは?と連想できます。
難しい話なのでもう少し詳しく解説します。問(3)では \(B_k=k^n(A_k-1)\) の \(0\) に収束する項である \(A_k-1\) を下式を利用して書き換えたんでした。
$$A_k-1=-\frac{\pi^2}{4}\frac{1}{(k+2)(k+1)}A_{k+2}$$
上式は両辺どちらも \(0\) に収束する訳ですが、 右辺 \(-\frac{\pi^2}{4}\frac{1}{(k+2)(k+1)}A_{k+2}\) は \(A_{k+2} \to 1\) であることから \(k^{-2}\) のオーダーで \(0\) に収束することも読み取れます。左辺の形だと極限値が \(0\) であることしかわからないのに対し、右辺は極限値に加えて収束のオーダーに関する情報も得られる訳です。すなわち、左辺 \(A_k-1\) よりも右辺 \(-\frac{\pi^2}{4}\frac{1}{(k+2)(k+1)}A_{k+2}\) の方が極限に関する情報に富んでいる訳です。問(3)はこの情報を利用して不定形を解消した格好になります。
この着眼点を本問にも当てはめれば、 \(B_k-B\) を \(B_{k+2}\) の式で書き換えれば、極限のオーダーに関する情報が得られるのでは?という発想に至る訳です。このアイディアがひねり出せれば勝ちです。
上記の \(A_k\) の漸化式を、 \(B_k=k^2(A_k-1) \Leftrightarrow A_k-1=\frac{B_k}{k^2}\Rightarrow A_{k+2}=\frac{B_{k+2}}{(k+2)^2}+1\) を用いて書き換えれば、
$$A_k-1=B\frac{1}{(k+2)(k+1)}A_{k+2}$$
$$\Leftrightarrow \frac{B_k}{k^2}=B\frac{1}{(k+2)(k+1)}\left(\frac{B_{k+2}}{(k+2)^2}+1\right)$$
$$\Leftrightarrow B_k=B\frac{k^2}{(k+2)(k+1)}\left(\frac{B_{k+2}}{(k+2)^2}+1\right)$$
$$=B\left(\frac{k^2}{(k+2)^3(k+1)}B_{k+2}+\frac{k^2}{(k+2)(k+1)}\right)$$
$$\Leftrightarrow B_k-B=B\left(\frac{k^2}{(k+2)^3(k+1)}B_{k+2}+\frac{k^2}{(k+2)(k+1)}-1\right)$$
$$=B\left(\frac{k^2}{(k+2)^3(k+1)}B_{k+2}+\frac{k^2-(k+2)(k+1)}{(k+2)(k+1)}\right)$$
$$\Leftrightarrow B_k-B=B\left(\frac{k^2}{(k+2)^3(k+1)}B_{k+2}-\frac{3k+2}{(k+2)(k+1)}\right)$$
が得られます。最終的に得られた式の右辺について、 \(\frac{k^2}{(k+2)^3(k+1)}B_{k+2}\) は(2次式)/(4次式)なので \(k^{-2}\) のオーダーで収束し、かたや \(\frac{3k+2}{(k+2)(k+1)}\) は \(k^{-1}\) のオーダーで収束するため、上式()は \(k^{-1}\) のオーダーで \(0\) に収束することがわかります。狙い通りオーダーの情報が入手できました。
最終的に得られた式の両辺に \(k^r\) を掛ければ、
$$C_k=k^r(B_k-B)=Bk^r\left(\frac{k^2}{(k+2)^3(k+1)}B_{k+2}-\frac{3k+2}{(k+2)(k+1)}\right)$$
$$\Leftrightarrow C_k=Bk^{r-1}\left(\frac{k^3}{(k+2)^3(k+1)}B_{k+2}-\frac{k(3k+2)}{(k+2)(k+1)}\right)$$
となり、右辺の()は \(-3\) に収束するため、 \(C_k\) が \(C \neq 0\) に収束するためには \(r-1=0\) が必要で、このときの極限値は \(C=-3B\) となる訳です。
以上より、求める値は \((p,q,r)=(4,3,1),\space C=-3B=\frac{3\pi^2}{4}\) と求まります。
解説は以上です。お疲れ様でした。

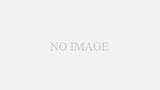
コメント